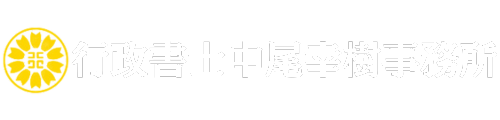【就労資格証明書】在留資格の就労範囲を明確に!企業と外国人双方に便利な活用方法


日本で働く外国人の皆さんの中には、「自分の在留資格ではどこまで働けるのか」「転職は可能なのか」「副業はできるのか」といった疑問や不安を抱えている方が少なくありません。特に日本の就労に関する法制度は複雑で、日本語の壁もあり、正確な情報を得ることが難しい状況にあります。
在留資格(ビザ)によって就労できる範囲は異なり、知らないうちに在留資格に反する活動をしてしまうと、ビザの更新が困難になったり、最悪の場合は強制退去の対象となることもあります。
そこで今回は、あなたの就労可能な範囲を明確に示す「就労資格証明書」について、その意義や取得方法、活用法までを分かりやすく解説します。日本での安心したキャリア形成のために、ぜひ参考にしてください。
この記事を読むとわかること
- 技術就労資格証明書とは何か、なぜ必要なのか
- 就労資格証明書の申請方法と必要書類
- 在留資格別の就労可能な活動範囲
- 転職や副業を考える際の注意点
- 就労資格に関する専門家相談の重要性
- 1. 外国人就労者が抱える在留資格と就労範囲の悩み
- 2. 就労資格証明書とは?あなたの「働ける範囲」を明確にする公的書類
- 3. 就労資格証明書がないと雇ってもらえないと聞いたけど本当?
- 4. 就労資格証明書を取得しておく3つのメリットとデメリット
- 4.1. 就労資格証明書を取得する3つのメリット
- 4.1.1. 1. 在留期間更新時の不許可リスクを軽減
- 4.1.2. 2. 転職や業務変更時の心理的安心感
- 4.1.3. 3. 不法就労の防止と企業のリスク管理
- 4.2. 就労資格証明書を取得するデメリット
- 4.2.1. 1. 申請手続きの複雑さと手間
- 4.2.2. 2. 取得までの時間的制約と不確実性
- 5. 就労資格証明書の取得方法と申請手続きの流れ
- 5.1. 申請の基本情報
- 5.2. 申請できる人
- 5.3. 申請に必要な書類と手続きの流れ
- 5.4. オンライン申請について
- 5.5. 申請時の注意点
- 6. まとめ
初回相談は無料
お気軽にお問い合わせください。
2024年最新【特定技能】基本情報|複雑な制度をわかりやすく解説
特定技能の基本情報から申請手順まで詳しく解説。多くの対象分野、必要条件、申請方法、就労時の権利義務を網羅。日本でのキャリアスタートに最適な在留資格!今から人生を変えましょう!
外国人就労者が抱える在留資格と就労範囲の悩み
日本で働く外国人の皆さんは、仕事の内容やキャリアに関する悩みに加え、在留資格(ビザ)による制約という独特の課題に直面しています。私たちの事務所には、こんな相談が日々寄せられています。
「現在の会社を辞めたらビザはどうなるのか」 「IT業界から別の業界への転職は可能か」 「副業やフリーランスとして働くことはできるのか」 「週末だけアルバイトをしても問題ないのか」
これらの悩みの根底には、在留資格による「就労範囲の制限」と「その範囲が明確でない」という二つの大きな要因があります。在留資格により認められる活動の範囲は法令で定められていますが、実際には自分の資格でどこまでの活動が認められているのか、分かりにくい場合が多いのです。
例えば、技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つエンジニアが、自分のスキルを活かして別の業界で働けるかどうかは、具体的な業務内容によって判断が分かれます。こうした「グレーゾーン」に悩む外国人就労者は少なくありません。また、転職の際は「在留資格に合致する仕事に就かなければならない」という制約があることを理解していても、具体的にどの仕事が該当するのかを判断するのは容易ではありません。
こうした悩みを解消するための有効な手段の一つが、次に紹介する「就労資格証明書」です。
*2019年から単純労働とされる分野も一部開放されました
就労資格証明書とは?あなたの「働ける範囲」を明確にする公的書類
就労資格証明書とは、出入国在留管理庁(入管)が発行する公的な証明書で、あなたが日本で行うことができる「収入を伴う活動(就労活動)」の範囲を明確に示すものです。
この証明書は入管法第19条の2に基づいて発行され、あなたの在留資格に応じて認められる就労活動の内容が具体的に記載されます。これにより、あなた自身も、雇用主となる企業も、どのような仕事ができるのかを正確に把握できるようになります。
第19条の2
出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人から申請があつたときは、法務省令で定めるところにより、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書を交付することができる。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方であれば、その専門分野に関連する業務に就くことができますが、その具体的な範囲は解釈が分かれることもあります。就労資格証明書があれば、「私はこのような業務に就くことができる」と明確に示すことができるのです。
ただし、重要なのは就労資格証明書自体は「許可書」ではないということです。あくまで現在の在留資格で認められている活動範囲を明確に示すものであり、新たに何かを許可するものではありません。在留資格で認められていない活動をするためには、別途「資格外活動許可」などの手続きが必要になります。
資格外活動許可を詳しく知りたい方にお勧めの記事
就労資格証明書がないと雇ってもらえないと聞いたけど本当?
そんなことはありません。就労資格証明書がなくても、あなたは合法的に就労できます。
入管法(出入国管理及び難民認定法)では、この証明書の有無による雇用差別を明確に禁止しています(第19条の2第2項)。
第19条の2第2項
何人も、外国人を雇用する等に際し、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動が明らかな場合に、当該外国人が前項の文書を提示し又は提出しないことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
つまり、企業はあなたがこの証明書を持っていないという理由だけで不利益な扱いをすることはできません。
とはいえ、転職活動では自分の就労できる範囲を明確に示せることは大きな強みになります。証明書があれば、面接官に「私はこの仕事を法的に行える資格がある」と具体的に証明でき、採用担当者の不安を解消できるでしょう。
特に外国人採用に慣れていない企業では、この安心感は採用判断を後押しする重要な要素となります。
就労資格証明書を取得しておく3つのメリットとデメリット


就労資格証明書を取得する3つのメリット
1. 在留期間更新時の不許可リスクを軽減
就労資格証明書を取得することは、在留期間更新をよりスムーズに進める上で大きな助けとなります。
就労資格証明書の取得によって、現在の就労内容が在留資格の範囲内であると入国管理局が公式に認めたことになります。つまり、「あなたの仕事内容は在留資格に適合している」という"お墨付き"を得たことになるのです。これは在留期間更新時の審査において、就労活動の適法性に関し疑われるリスクを大幅に軽減します。
2. 転職や業務変更時の心理的安心感
日本での就労において、転職や業務内容の変更は外国人にとって不安を伴う出来事です。特に「新しい仕事が在留資格の範囲内に収まるのか」という懸念は、キャリア選択を躊躇させる要因となっています。
就労資格証明書の取得は、この不安を解消する実質的な手段となります。証明書によって新たな職務が在留資格に適合することが公的に認められれば、安心して新しい職場に踏み出すことができます。
また、この証明書は雇用主側にとっても、外国人雇用に伴う不確実性を減らす貴重なツールとなります。採用担当者が「この外国人は合法的に当社の業務に従事できるのか」という疑問を抱く場合、就労資格証明書は明確な答えを提供してくれるのです。
3. 不法就労の防止と企業のリスク管理
就労資格証明書の重要性は、外国人本人だけでなく雇用する企業側でも同様です。
企業が故意でなくとも就労資格のない外国人を雇用してしまうと、「不法就労助長罪」という深刻な罪に問われるリスクがあります。この罪は「5年以下の懲役または500万円以下の罰金、あるいはその併科」という重い刑罰が定められており、企業の社会的信用にも大きなダメージを与えます。
就労資格証明書を確認することで、企業は採用予定の外国人が特定の業務に合法的に従事できることを事前に確認できます。これは企業のコンプライアンス体制の一環として非常に有効です。外国人雇用における不確実性を減らし、意図せぬ法令違反を防止するための「保険」として機能するのです。
特に外国人雇用の経験が少ない企業にとって、就労資格証明書は貴重な判断材料となります。在留カードだけでは分かりにくい「具体的にどのような業務に従事できるか」という情報を明確に示してくれるからです。
就労資格証明書を取得するデメリット
1. 申請手続きの複雑さと手間
就労資格証明書の取得には、いくつかの障壁が存在します。まず、申請書類の準備と申請手続きには相応の時間と労力を要します。特に転職に伴う申請では、新しい勤務先や活動内容の詳細が分かる資料を収集する必要があります。
また、申請書の作成には入管法に関する正確な知識が求められます。どのような情報をどのように記載すべきか、専門的な判断が必要な場面も少なくありません。特に在留資格の範囲内で認められる活動の説明が複雑な場合や、業種をまたぐ転職の場合などは、申請書の作成自体が高いハードルとなり得ます。
外国人本人が日本語に不慣れである場合、この困難はさらに増大します。入管関連の専門用語や法律的な表現は、ビジネスレベルの日本語力を持つ方でも理解が難しいことがあるのです。
2. 取得までの時間的制約と不確実性
就労資格証明書の発行には一定の時間を要します。
- 勤務先を変えていない場合:当日
- 勤務先を変えた場合(転職):1ヶ月~3か月程度
*在留管理局の混雑状況や申請内容の複雑さによってはさらに長引くこともあります。
以上のように、就労資格証明書の取得にはメリットとデメリットの両面があります。どちらを重視するかは個々の状況によって異なりますが、長期的な日本滞在を視野に入れている場合は、デメリットを踏まえつつも、取得することで得られる法的安定性というメリットは非常に大きいと言えるでしょう。専門家のサポートを得ることで、デメリットの多くは軽減できる点も考慮すべきポイントです。
初回相談は無料
お気軽にお問い合わせください。
就労資格証明書の取得方法と申請手続きの流れ
就労資格証明書の取得は比較的シンプルですが、必要書類や手続きを正確に理解しておくことで、スムーズに進めることができます。ここでは、申請から取得までの流れを詳しく解説します。
申請の基本情報
- 申請場所: 住居地を管轄する地方出入国在留管理局(入管)
- 受付時間: 平日9:00〜12:00、13:00〜16:00(地域により異なる場合あり)
- 手数料: 2,000円(収入印紙で納付。オンライン申請の場合は1,600円)
- 標準処理期間: 当日〜数週間(勤務先変更がある場合は1〜3か月かかることも)
申請できる人
申請提出者として認められているのは以下の3つのカテゴリーです:
- 申請人本人:最も基本的な形態で、日本での滞在を希望する外国人ご自身が直接申請を行うケースです。これは自分の意思で手続きを進めたい方に適しています。
- 代理人(法定代理人):申請人が未成年者である場合や、何らかの理由で自ら手続きを行うことが困難な場合に、親権者や後見人などの法定代理人が本人に代わって申請を行います。この制度は申請人の権利を保護するための重要な仕組みです。
- 申請取次者:さらに細分化すると、以下の2種類があります。
- 地方出入国在留管理局長から特別な承認を受けた者:
- 申請人が勤務する会社や所属機関の職員
- 申請人が研修や教育を受けている教育機関の職員
- 技能実習などの監理団体の職員
- 外国人の円滑な受入れを目的とする公益法人の職員
- 地方出入国在留管理局長に届出をした法律の専門家:
- 弁護士
- 行政書士
- 地方出入国在留管理局長から特別な承認を受けた者:
実際の申請において、どの申請提出者を選ぶかは状況によって異なります。例えば、日本語に不安がある場合や、複雑な案件を抱えている場合には、専門知識を持つ行政書士や弁護士に依頼することで、申請書の作成ミスを防ぎ、審査をスムーズに進めることが可能になります。
申請に必要な書類と手続きの流れ
申請書の入手と記入
就労資格証明書交付申請書は、入管のウェブサイトからダウンロードできます。日本産業規格A4サイズの用紙に印刷して使用します。記入は日本語で行います。
必要書類の準備
- 就労資格証明書交付申請書
- 資格外活動許可書を提示(同許可を受けている場合)
- 在留カードまたは特別永住者証明書の提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示
- 旅券又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
転職等し勤務先や活動内容に変更がある方は、雇用契約書、会社の登記事項証明書、会社案内などの追加書類が必要になることがあります。
入管への申請
準備した書類を持って、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に行きます。窓口で申請書と必要書類を提出し、手数料を納付します。
証明書の受け取り
審査の結果、発行が認められれば就労資格証明書が交付されます。勤務先や活動内容に変更がない場合は当日発行されることが多いですが、変更がある場合は審査に時間がかかることがあります。
オンライン申請について
2020年3月から、在留申請オンラインシステムを通じて就労資格証明書の申請ができるようになりました。以下の点が特徴です:
- 自宅やオフィスからインターネットで申請可能
- 手数料が1,600円と通常申請より安い
- 申請後の進捗状況をオンラインで確認できる
ただし、オンライン申請には事前登録が必要であり、対象となる方も限られています。詳細は下記、入管のウェブサイトで確認してください。
申請時の注意点
- 正確な情報提供
申請書には正確な情報を記入しましょう。虚偽の申告をすると、審査に悪影響を及ぼすだけでなく、在留資格の取消しにつながる可能性もあります。 - 活動内容の具体的な説明
特に勤務先や活動内容に変更がある場合は、新しい活動が在留資格の範囲内であることを示すため、具体的かつ詳細な説明が必要です。職務内容、使用する専門知識・技術、業務上の役割などを明確に記載しましょう。なお、この手続きは不服申し立てが認められていません。 - 証明書の有効期間
就労資格証明書の有効期間は基本的に在留期間と同じです。在留期間が更新されたり、在留資格が変更されたりした場合は、新たに申請する必要があります。 - 代理人による申請
本人が直接申請できない場合は、法定代理人、地方出入国在留管理局長から承認を受けた申請取次者(所属機関の職員、弁護士、行政書士など)が申請することもできます。
勤務先に変更のない就労資格証明書の取得自体はそれほど複雑ではありませんが、勤務先や活動内容の変更がある場合は、事前に行政書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のサポートを受けることで、スムーズな申請と確実な取得が期待できます。
まとめ
就労資格証明書は、日本で働く外国人の方にとって重要な書類です。この証明書により、在留資格で許可される就労の範囲が明確になり、転職活動や在留資格の更新手続きがスムーズになる場合があります。また、企業側は不法就労のリスクを回避でき、採用時の安心感につながります。取得には通常1~3ヵ月程度かかりますが、日本での安定したキャリア形成に役立つ書類です。就労に関する不安や疑問がある場合は、横浜・横須賀エリアの行政書士や入国管理局の窓口に相談することで、適切なサポートを受けることができます。
▼この記事は主に以下の資料・サイトを基に執筆しました

中尾幸樹
「お客様一人ひとりの人生に寄り添う」を理念に掲げる当事務所は、神奈川県逗子市を拠点とする行政書士事務所です。特に力を入れているのが、在日米軍関係者と、そのご家族に向けた日本での在留資格取得サポート。現職の米軍基地職員なので、内部事情に精通しており、特別なアプローチが可能。まずは無料の初回相談でお気軽にご相談ください。
【受け入れ機関必読】外国人を支援する計画が適切かどうかのポイントを詳細解説 4/4
特定技能外国人の支援計画作成に関する実務解説です。法務省が定める基準への適合要件、2か国語での作成義務、対面・オンラインでの支援実施など、企業担当者が押さえるべきポイントを分かりやすく解説しています。支援計画の作成から実施まで、具体的な注意点を網羅的に紹介します。
【受け入れ機関必読】特定技能外国人支援計画の適正な実施の確保の基準 3/4
特定技能外国人の受け入れに必要な支援体制の7つの要件を、特定技能基準省令2条2項に基づき詳しく解説。支援責任者・担当者の選任基準から、コミュニケーション体制の整備、文書管理の方法、定期面談の実施要件まで、中小企業の実務担当者向けに具体的な対応方法をわかりやすく説明します。登録支援機関への委託についても触れています。
【2024年保存版】特定技能所属機関の4つの基準と3つの義務
2024年現在最新|特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき4つの基準(雇用契約・受入れ機関の適格性・支援体制・支援計画)と3つの義務(契約履行・支援実施・行政届出)について解説。要件の詳細と注意点を外国人ビザ専門の申請取次行政書士がわかりやすく説明します。
【受け入れ機関必読】特定技能外国人受け入れ機関自身の基準 2/4
特定技能外国人を受け入れる企業が満たすべき13の基準を詳しく解説。労働法令の遵守、雇用管理、外国人の権利保護など、受け入れ機関として必要な要件をわかりやすく説明。実務担当者必見の具体的なガイドラインを提供します。
【受け入れ機関必読】特定技能の外国人との雇用契約の要件を詳細解説 1/4
特定技能外国人を受け入れるためには、受入れ機関として様々な基準を満たし、適切な体制を整備する必要があります。本記事では、特定技能所属機関・受入れ機関がクリアしておかないとならない4つの基準の一つである特定技能外国人との雇用契約の締結と適切な労務管理について詳細に解説をしています。
外食業の特定技能外国人受入れガイド:制度の基礎から注意点まで丁寧に解説
外食業界における特定技能制度の最新動向と実務知識を解説。令和6年からの新たな受入枠の特徴、制度活用のメリット・デメリット、在留資格の種類と要件、そして受入機関に求められる基準まで、外国人材の採用・雇用に必要な情報を網羅的に紹介します。人材不足解消の切り札として注目される特定技能制度の全容が分かります。
免責事項
本記事は入管法に関する一般的な情報提供を目的としており、執筆時点での法令・運用に基づいています。
入国管理局の審査基準や運用は随時変更される可能性があり、また個々の事案により判断が異なる場合があります。記事の内容に基づく申請や判断により生じたいかなる結果についても、著者および運営者は一切の責任を負いません。